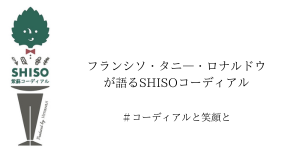9種の聖なるハーブ
流離人ウォーディン。
このように絵画などでは一般に、 片目が無い、長い髭を持った老人 で、つばの広い帽子を被り、グング ニルという槍を持った姿で表される。
スウェーデンの画家 ゲオルク・フォン・ローゼンによる。(1886年)
| 9つの薬草と呪文 九つの薬草の呪文はウォーデンについて触れられる 二つの古英詩のうちの一つです。 Wyrm com snican, toslat he man;
A snake came crawling, it bit a man. Then Woden took nine glory-twigs, Smote the serpent so that it flew into nine parts. There apple brought this pass against poison, That she nevermore would enter her house.
上の文は古英語、下の文は現代英語です。
日本語でいう古語と現代語みたいな関係です。
訳 蛇が這い来たりて人傷つけたり。
wyrmを現代語ではA snakeとなっていますが、 いわゆる蛇状の怪物を意味してると考えられています。
ille and finule, felamihtigu twa,
訳 タイムとフェンネルを、いと力強き双方を、 薬草を、賢明なる主は創造(つく)りたり、 てんにおわす神々しき者は、懸られし時に。 これを七つなる世界に捉え送りたり、なべて貧なるもの、 富なるものの慰めとて。 これは痛みに効き、毒に効く、 これは三十と三(の疾患)に対し。 悪魔の仕業に対し、突然のたぶらかしに対し、 悪しき者共の呪詛に対し。
この部分では、薬草の創造主を「天におわす神々しき者」 とし、彼が「懸られし時に」作ったとしています。
ここに出てくる九つなる栄光の枝、 すなわち9種の薬草がこれにあたると言われています。
①マッグウィルト(Mucgwyrt、ヨモギ) 他の研究者はベトニーと定義しています)
※もしもベトニーであれば 異臭を放ち皮膚炎を起こしたりします。 良く飲まれています。 恐らくコモンタイムを指していると思います。 チャービルだという説もあります。
呪文の終わりには、先に述べた薬草を用いるために 砕いて粉末にし、古い石鹸やリンゴの果汁と混ぜ合わせるよう 散文で書かれてあり、さらに水と灰から練り物を作り、 これにフェンネルを入れて煮立て、 泡立てた卵と混ぜ合わせたのち、 出来た軟膏を塗るように説明しています。
加えて、調合する前の薬草とリンゴに向って 呪文の歌を三度詠唱すること、 患者の傷口と両耳、患者本人に向って 膏薬を塗る前にも呪文を唱えること、 と指示しています。
|